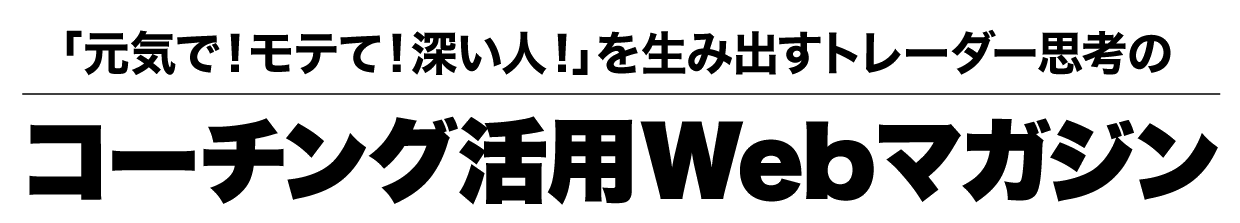子どもと暮らしていると、とても楽しかったり、嬉しかったり、新しい発見があったり、充実した時間が過ごせます。
一方で、
落ち着かない、「かまってかまって」が多い、話を聞いてくれない、何度も同じことを言って聞かせる…
などなど、頭を悩ませることもあるのではないかと思います。
我が家も例外ではなく、息子たちの傍若無人なふるまいに頭を悩ませる日々でした。
そんな私ですがタナカミノルさんの音声コーチングを聞いて、「これを子育てに応用できないか」と色々試した結果、子供たちにみるみる変化が訪れました。
その時にうまくった5つの工夫とどんな風に変化したのかを具体的にレポートします。
まさにギャング!やりたい放題の息子たち…
わが家には3歳と5歳の息子がいます。
2人になると1人だったときとは比べ物にならないくらいに騒がしくなってきます。
気づいたら、
- 買ったばかりのダイニングテーブルに傷や凹みが
- 引っ越したばかりの部屋の壁に立派なお絵描きが
- 床が見えなくなるくらいにおもちゃが散乱し
- 大きな声で叫ぶ
- 下の階の人がびっくりするくらいに部屋中をぴょんぴょん飛び跳ねまわり
- 扉という扉を開けたり締めたりドッタンバッタン ,etc.
色々注意しても、聞く耳を持ちません。
まさにギャングと言っていいほど、傍若無人なふるまいでした。
まずは、それぞれの〇〇を観察し、満たす
注意する以外に何かできないかと思い、以前タナカミノルさんの音声コーチングで聞いたアプローチをためしてみることしました。
実はこれは夫婦関係で試してうまくいったのが実証済みだったので、子育てにも使ってみようと思ったわけです。
コーチングで聞いたこととは、愛情の表現と受け取り方が人それぞれ異なるので、それぞれにアプローチを変えたほうがうまくいくというものでした。
このアプローチが直接的に子供たちのドッタンバッタンをしずめるのに効果があるのかは、正直わからなかったのですが、まずは思いついたことを試してみようと始めてみました。
ふたりの違いがみえてきた
2人の性格の違いや興味の先が異なることは感じていましたが、愛情の伝え方としてはむしろ、分け隔てなく平等にしようと考えており2人とも同じように接してきました。
この「平等にしなければ」というのは、親として子に与えるという本質的な意味ではその通りなのですが、細かいアプローチは変えたほうがいいのではないか?と思ったのです。
なので、まずはじっくり2人を観察してみることにしました。
長男はよく私たちにプレゼントをくれます。
折り紙で折ったカブトやハート。
お手紙。
お絵かき。
また、率先してお手伝いをしてくれます。
一緒に野菜を切ったり。
ゴマをすったり。
お掃除したり。
次男は抱っこが大好きです。
明らかにお兄ちゃんよりも抱っこを求めてくる頻度が多く、気づいたら膝の上に乗っています。
そしていつも「大好き」と私たちに伝えてくれます。

じっくり観察することで、2人の違いが見えてきました。
つまり
- 長男はお手伝いやプレゼントをすることで愛情を表現してくれる
- 次男は長男とは違い、体に触れることや言葉で愛情を表現してくれる
そこで、それぞれにあわせた方法で愛情を満たしてあげることにしました。
例えば、長男はがんばりやさんで普段は自分のことは自分でデキる子です。
ふだんできることなのに
「今日はできない」
と甘えてくることがありました。
いつもなら
「自分でできるでしょ!」
と促してしまうところです。
しかしこれは愛情を欲しているサインであると受け止め
「今日はやりたくない気分なんだね。助けてあげるよ」
とお手伝いをしてあげるようにしました。
次男は落ち着かないときは特に
「抱っこ!抱っこ!」
とせがんできます。
いつもなら
「今忙しいから後でね」
といって後回しにしていたところです。
しかし、これも同じようにサインと受け止め次男みずから離れるまでずっと抱っこをし続けました。
そうするうちに、少しずつ息子たちが穏やかになっていきました。
今までの落ち着きなくドタバタしたり騒いだりする頻度がみるみる減って、穏やかな時間が増えてきたのです。
これがまず1つ目のポイントになります。

まずは自分が子供の話をしっかり聞いてみる
次に2つ目のポイントです。
親も仕事や家事をしていたら、話しかけられても片手間に相手をしてしまったり、後回しにしてしまうこともしばしばです。
当たり前のようにやってしまっていることですが、改めて考えてみると、それって私たち親が子ども達の話をきちんと聞いてあげていないということです。
親は子どもに「きちんと話を聞きなさい!」と押し付けますが、親は子供の話をきちんと話をきかない…、これでは子どもたちが話を最後まで聞いてくれないのは、当然なのかもしれません。
なのでまず私たち親が集中して子ども達の話を最後まで聞くことを意識することにしました。
息子に話しかけられたら、やっていることを中断して、息子と目線を合わせ途中で遮らずに最後まで話を聞きます。
「うんうん、そうだったね」
どうしても中断できない場合には
「今手が離せないので後で必ず聞くからまた教えてね」
終わり次第すぐに息子のところに行き、話を聞きます。
「待っていてくれてありがとう。さっきのお話の続き聞かせてくれる?」
必ずあなたの話を最後まで聞きますよ、というスタンスを息子たちに見せ続けたのです。
また、私たちが息子たちに話しかけるときは集中している時間は避けて
「今話しかけていい?」
と確認してから話すようにしました。
結果として、息子たちが最後まで話を聞いてくれることが明らかに増えました。
すごいぞ!フロー(没頭)体験
1つ目と2つ目のポイントを経ると、子供たちの土台が安定したのか、息子たちが徐々に変化していることに気がつきました。
新しい発見したときのびっくりした顔や集中して取り組むときの真剣な顔が以前に比べて格段に増えてきたのです。
この集中できている状態と途中で飽きて投げ出してしまう状態との違いを紐解くカギもまた音声コーチングの中にあったのです。
フローってなに?
集中して作業をしていて気づいたらすごい時間がたっていた、ってことは誰でも経験したことがあるのではないでしょうか。この集中し没頭している状態を「フロー」と呼びます。
一方で、やる気が出なかったり、集中できなかったり、いざ集中しても続かなかったりという経験も同じくらいあると思います。
では、この集中した状態を狙って作ることができたら、どれだけ作業がはかどるか。

私自身、「フロー」を意識することでこれまで何日もかかってやっと作成していた資料が、一日で終わることがわかりました。
そして終わった時に「やりきった感」や「達成感」といったここちよい感覚がありました。自分が確実に前進できている実感がありました。
いま、息子たちが集中して没頭している状態がまさにこの「フロー」状態なのだと観察して思いました。
息子たちがフロー体験を繰り返していけば、それはそれは充実した日々になるだろうし、できる限りたくさんの「フロー体験」をして充実した日々を過ごしてほしい、と心から思いました。
フロー体験を増やすには?おもちゃを減らして見えてきた変化
フロー体験をより多く体験してもらうために私たち親ができることを考えました。これが3つ目のポイントです。
まず、子ども達の気を散らすモノを減らすことから始めました。
テレビの電源を入れなくなりました。
刺激になるだけのおもちゃを減らして、集中できるようなおもちゃを並べました。
息子たちの目の前でスマホやパソコンを触ったりしないようにしました。
息子たちに
「今日は何やりたい?」
と自らやりたいことを選んでもらいました。
家で折り紙をしたり。
公園で砂場でお山を作ったり。
息子たちが集中し始めたら、できる限り中断させないように気をつけました。
フローに入りやすい状態の「ちょうどいい」を探して
「フロー」に入っているときの息子たちの顔は真剣そのもの。とてもいい顔をしています。
しかし、集中していたと思ったら途中で投げ出してしまったり、飽きてしまうこともよくありました。
難しすぎると途中でイヤになってしまいます。
簡単すぎると途中で飽きてしまいます。
「フロー」に入るためには程よい難易度であることが必要なのです。
長男がやっていることを次男はやりたがりますが、当然ながら難しいこともあります。その場合には、ヒントを出したり、言い方を変えたり、手助けをしてあげたりしました。
長男にはちょっと難しくて、でもがんばればできそうなおもちゃや遊び方を提案してみたりしました。
つまり、それぞれ「フロー」に入りやすいちょうどいい難易度を調整するのを手助けしてみたのです。
結果として、2人とも「フロー」の時間が増えてきていると感じています。

褒めなくても子供は十分満足できる
4つ目のポイントは「成果を褒めることをやめた」です。
かわりに、がんばった過程を認め、それまでやってきたことを事実として認めました。
「すごいね」「えらいね」などのいわゆる報酬言葉をなるべく使わず、
「できたね」「がんばったね」「ありがとう」「助かった」などの言葉を使うようにしました。
単純に褒めるのではなく、がんばった過程に対して「驚い」て、やってきた事実に対して「関心を持つ」という戦略です。
それによって、褒めてほしいとか、注目がほしいといった、欲求を満たすのではなく
子どもに対して
「いつでもあなたに関心がありますよ」
ということを伝えているだけで子どもは十分満足してくれる事がわかりました。
これもタナカミノルさんの音声コーチングで学びました。
叱らなくても学ぶ方法はある
5つ目のポイントは、失敗は学習するチャンスと考えるようにしたことです。
そう考えることで、「叱る」以外の対応ができるようになりました。
例えば
テーブルの端に置いてあるコップに手があたり今にもこぼれてしまいそうな状況だとします。
今までの私たちは
「こぼれちゃうよ」
と前もってコップを安全な場所に動かしたり
こぼしてしまうと
「何やってるの!」
と叱ってしまっていたと思います。
しかし、失敗しないように前もって親が動いてしまうことで、「子どもは失敗=学習のチャンス」を失ってしまいます。
今では
「こぼしてしまった」という体験を実際にしてもらい
「なぜそうなったのか?」
「どうすれば繰り返さないか?」
「もしそうなった場合にどう対処すればいいのか?」
を一緒に考える様になりました。
その結果、自分で気づいてコップを安全な場所に動かせることが増えてきました。
こぼしたとしても、自分でタオルを持ってきて拭く事ができるようになっています。
ギャングはいなくなった?最近のギャングたち
息子たちは以前と比べて穏やかになり、毎日のようにフローの時間を持ち、少しづつできる事柄も増えて充実した時間を過ごせていると思います。
ここまでやった5つの工夫を改めてまとめると
- それぞれに愛されていると感じやすいコミュニケーションをする
- 親がきちんと自分たちにむきあっていることを実感させる
- フロー体験をサポートする
- 褒めずに子供を満足させる
- 失敗は学習するチャンス、叱らずに学びにつなげる
といった感じです。
もちろん子どもですから、時にギャングが顔をだすこともありますし、成長に応じてできることは他にもいっぱいあると思います。
これからも色々検証をしていくつもりですが、この記事が子育てに悩む方々の参考や助けになれば嬉しいです。