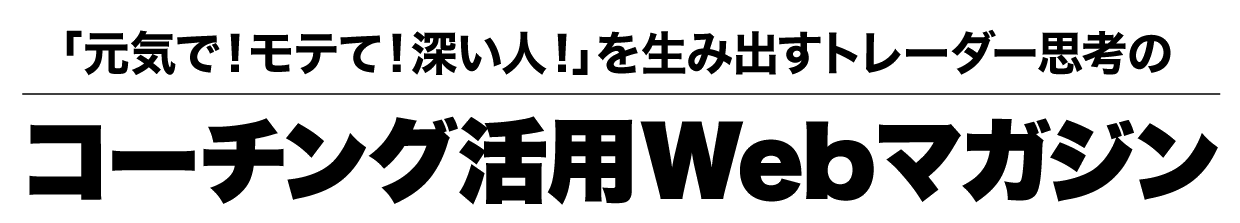あなたは、読書についてどう感じますか?
「実は活字が苦手で……」という方もいれば、「時間があると読んでます」という方も、いらっしゃると思います。
わたしは、両方の経験があります。
苦手な時といえば、仕事で使うために手に取った本を読もうとしても、ちっとも読み進められない時期がありました。
外国語で書かれているわけでもなく、普通の日本語の本なのに…です。
本を手にしても、読書は進まないまま、時間だけが過ぎてしまう。
それが繰り返されていくうちに、だんだんと本を手に取ることも嫌になっていきました。
全然読めない時とスラスラ読めた時の違い
全然読めない時は「一体、今の時間は、何をしていたんだろう」という後悔でいっぱいに
まず、読めない時ですが、もちろん書かれている文字は読めますし、単語の意味がわからないわけでもありません。
それでも、文章を読み進められない。
スマートフォンの通知で、ゲームのスタミナがあふれたことを知らされて、「消化しないと勿体無い」とアプリを起動してゲームをはじめてしまうことも、よくあることでした。
机に置かれた郵便物が気になりだして、封を開けてしまったり、散らかっている机の周りを整理を始めることもありました。
そうかと思えば、窓の外から聞こえてくる話し声や、近所のテレビの音が聞こえてきて、内容に注意が向いてしまう。
そうした出来事に気を取られてしまい、読書が進まないまま時間が過ぎてしまって、自分を責めてしまうことにもなっていました。
スラスラと読み進められた時は?
では、以前から本が読めなかったのかというと、スラスラと読めた時もありました。
たとえば、自習室や図書館などの静かな場所では、黙々と本を読めていました。
電車で運よく座席に座れた時には、本を読んでいて乗り過ごしてしまうこともありました。
好きな作家さんの新刊を手にしたときには、食事も忘れて夜更けまで読み続ける事もありました。
そうした時は、先の展開が気になり、周りのことも目に入らなくなって、夢中になり本を読んでいました。
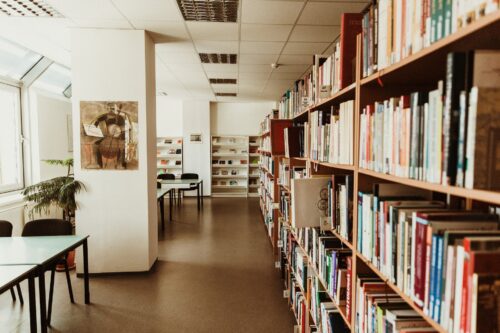
違いは何だろう
本を読めない状態と読み進められた状態と比べてみると、最初の段階で、スマートフォンや周りの音や物などが気になってしまい、読書に集中できていないことが大きいように思えました。
もちろん、読もうとする本に対する興味や関心が高いかどうかも関係しそうです。苦手な本や、押し付けられた本では、やはり読みたい気持ちもおさえられてしまいます。
そう捉えてみると、本を読む前の段階として、取り組むための環境が整えられていないために、焦ったり頑張ったりしても、空回りしていたように思います。
図書館などの静かな場所は、周りに気を取られないで読書ができていました。また、楽しみにしていた本は読みたい気持ちが高かったこともあり、集中できていたのだと思えました。
音声コーチングで、本を読めない状態の改善へ
音声コーチングに浸る
少し話は変わりますが、わたしは移動時間やちょっとした休憩中に、タナカミノルさんの音声コーチングを聴くことが多いです。
ひとつのテーマに対して様々な視点から説明をされることもあり、今まで見ていた物事がよりクッキリと見えてきます。
構成も工夫されていて、聴くタイミングによってピンとくる部分が違ったりします。
特に「何とかしたいな」という問題や、出来事があったときは、音声コーチングをランダム再生にして聴くようにしています。
ランダムに聴くことによって、自分の思い付きやこれまでの考えでは思いつかないつながりやヒントを得られることがよくあったからです。

ヒントになりそうなことは何か?
今回の場合は、読書がうまくいかない状態を何とかしたいと思いながら音声を聴いていく中で、関係しそうなこと、ヒントになりそうなことを見つける度にメモを取っていきました。
そうして集めたメモを整理していき、関係しそうな要素をまとめたのが、次の3つです。
- あれもこれもと手を出さないで、ひとつずつ行うことで、混乱せずに読書をすすめられるかもしれない。
- 静かな場所を選んだり、部屋を片付けたりして読書に集中できる環境を整えることで、気が散る状態を避けられそう。
- 何のために本を読むのかを明確にしてから読み始めることで、スマートフォンなどに注意を取られにくくできるかもしれない。
最善ではないかもしれませんが、まずはこの仮説に取り組んでみようと始めました。
集中して本を読むための工夫
注意をそらさないためにしたこと
最初に行ってよかったことは、読書を続けるための環境を整えることでした。
基本的なことですが、読書の前には集中できるように、机の周りを整理したり片付けることは忘れないように行っています。(「なんでこんなところに消しゴムのカスが?」と掃除を始めてしまい、読む気が消えることもありました)
スマートフォンもマナーモードにしたり、視界に入らないようにしまっておくことも準備としては大切なことでした。(ゲームのスタミナを先に消化しておくことで、ゲームを気にせずに読書に集中することにもなりました)
読書を始める時に、周りを気にせずに取り掛かれる状態を作ることは、気を散らさずに集中を続けることにもつながりました。
読みたい本であるからこそ、集中できる環境を作ってから読み始めることで深く味わえるようにもなったと感じています。

何のためかをハッキリさせる
楽しみにしている本だと、すぐにページを開いて読みたくなってしまうのですが、「この読書の目的は何だろう?」と自分に問いかけて、答えを紙に書いておくことで、読書の狙いが明確になり、押さえるポイントがしっかりします。
気乗りしない本の場合は、「ここだけは押さえておこう」という目星をつけられるので、なんとなく本を通読するだけで終わってしまうことも少なくなっていきました。
たとえば、「次の仕事で使いたい行動をひとつ見つける」という目的にして本を読んでいくことで、「やってみたいな」という部分が少し強調されて見えてきます。
ただ読むだけだと、「面白かった」「楽しかった」「ためになった気がする」で終わってしまうことも多かったのですが、行動をひとつ見つけて試すだけでも、本を読むことが、生活に変化を生み出すことにつながっていると感じられました。
読書中に、気になったこと、覚えておきたい事は、A4の紙に記録するようにもしました。
これには、自分の気になったポイントをまとめて書いています。
そのため、後で調べたりするときに役に立つだけでなく、「どんなことが書かれていたかな」と感じた時に全体を読み返さなくてもすむために、重宝しています。
全力で取り組むためのしくみ
追い込まれたり、焦っている時は、ついつい「あれもして、これもしなくては」といろいろと手を出すことで、何かやっている感じになることで安心したかったように思います。
全体の流れを先に決めておいて、順番に行っていくことで、次に何をするかが見えてきて、自分の中の読書の流れが整理できてきました。
まずは、周りを片付けて、読書にふさわしい環境を作る。
つぎに、読書の目的を明確にさせてから、本を読み始めます。
「当たり前のことじゃないの?」と感じられるかもしれませんが、わたしにとっては大切な手順となっています。
もちろん、読書の間ずっと集中し続けることができない時もあります。
そうした集中が途切れた時は、何かのきっかけがあったと考えて、途切れさせたものを見つけ、取り除けないかと工夫することで、さらにいい環境へと近づけていくことになります。
(夏の朝、涼しい時に読み始めて、暑さで集中して読めなくなってきたら、風を通すようにしたり、クーラーをかけたりといった小さな工夫です)

取り組みのこれから
意図せず生まれた副産物
取り組みを続けていく中で、手順が身についてくると、心の中で「目的は?」と思い浮かぶようになってきました。習慣がついていくにつれて、読書以外の時でも目的を気にかけることが増えていきました。
意図せずに変わってきたこととして、人ときちんと向き合うようになった点もあります。
以前なら、読書をしている時に声をかけられると、「今、読書なんだ」と即座に断ってしまうことが多かったのです。それが、声をかけられたときにも「目的は?」と思い浮かぶことで、「相手が求めることは何だろう」「どうなったらうれしいかな」と相手の気持ちに焦点が移るようになっていました。
(そもそも、本当に一人で静かに読書をしたいのだとしたら、声をかけられる環境は避けるべきだったわけですが……)
だんだんと自分の目的から、相手の目的へも目が向くようになって、少し視野が広がった気もしています。
この成功体験をもとに複利をきかせる
タナカミノルさんの音声コーチングの力を借りて、読みたいけれど、読み進められない苦痛に対する取り組みを行いました。取り組みを通して、自分の集中力へのアプローチを整理し工夫していく土台を作ることができました。
もしかしたら人によっては「読書ごときで大袈裟じゃない?」と思われたかもしれません。
でも、集中するための環境を整え、目的を意識し、ひとつずつ進めることは、読書だけでなく他のことにもつながっていくとも感じています。
つまり最初は小さな成功体験でも、それを複利の一歩目として活かしていけば、どんどんと成功体験は大きくなるということです。
もしあなたも何か変化を起こしたければ、「つまらないな」と思わずに、小さなことから取り組んでみてはいかがでしょうか。
何かひとつでも、あなたの刺激となったとしたら、幸いです。
最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。
→筆者の変化のきっかけになった「30日間のオンラインコーチングプログラム」が今だけ無料で体験できます。詳しくはこちら